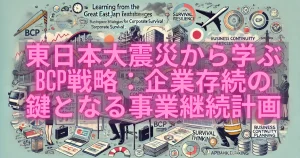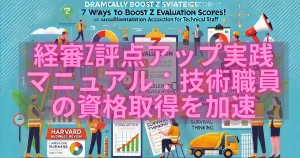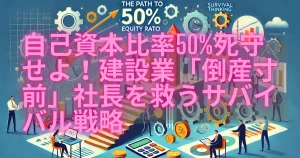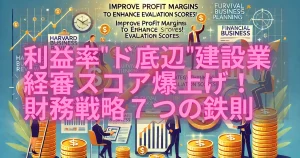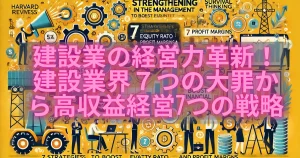本レポートは、経営コンサルティング業務支援を目的とし、スーパーゼネコン5社(鹿島建設、大林組、大成建設、清水建設、竹中工務店)の2025年3月期(竹中工務店は2024年12月期)決算に基づく包括的な財務・戦略分析を提供するものである。
2024年度のスーパーゼネコン各社は、旺盛な国内建設需要を背景に増収基調を維持した。特に、資材価格高騰分の価格転嫁や採算性を重視した選別受注が進んだ結果、利益率が大きく改善し、鹿島建設、大林組、大成建設は前期比で大幅な増益を達成した 。一方で、建設業界の構造的課題である「2024年問題」に起因する労務費上昇と深刻な人手不足は常態化しており、各社は生産性向上を最重要経営課題と位置づけ、BIM(Building Information Modeling)を核とした建設DX(デジタルトランスフォーメーション)への投資を加速させている。
事業ポートフォリオの観点では、利益率の高い不動産開発事業が建設事業の収益変動を補完し、業績の安定化に寄与する傾向がより鮮明になった。特に海外の不動産開発事業は、鹿島建設や大林組にとって重要な収益柱へと成長している 。海外建設事業は、北米市場の堅調さやアジア地域の回復が見られる一方、地域や子会社によって業績に濃淡があり、リスク管理の重要性が増している。
財務戦略においては、資本効率を意識した経営への転換が明確である。ROE(自己資本利益率)の向上を最重要指標の一つに掲げ、政策保有株式の縮減、積極的な自己株式取得、増配といった株主還元強化の動きが顕著に見られる 。
今後の展望として、短期的な建設需要は堅調に推移すると見られるが、中長期的には人手不足という供給サイドの制約が成長の足枷となるリスクを内包している。この構造的課題を克服し、持続的成長を遂げるためには、技術力による生産性の抜本的な向上と、不動産、再生可能エネルギー、コンセッション事業といった非建設事業における収益基盤の多角化・強化が各社の将来を左右する鍵となるだろう。
第1章:建設業界の事業環境とマクロトレンド分析
1.1 2024年問題の本格化と人手不足の常態化
2024年4月、建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、業界は深刻な構造変化に直面している 。この「2024年問題」は、単なる規制強化にとどまらず、長年続いてきた長時間労働を前提とするビジネスモデルの根幹を揺るがす事態となっている。
人手不足の深刻化を示すデータ 建設業界の人手不足は、各種統計データによって客観的に裏付けられている。帝国データバンクの調査によれば、2025年上半期の人手不足を起因とする倒産は202件に達した 。また、正社員が不足していると感じる企業の割合は「建設」が68.1%と、全産業の中で最も高い水準にある 。
有効求人倍率も職種によって極めて高い数値を示しており、建設躯体工事従事者で10.46倍、土木作業従事者で7.43倍と、求職者に対して求人が圧倒的に不足している状況が続いている 。マイナビの調査でも、建設業界の雇用人員判断D.I.(人手不足感)は悪化傾向にあり、全産業と比較しても強い不足感が示されている 。
具体的な影響 この構造的な人手不足と労働時間規制は、建設プロジェクトの遂行に具体的な影響を及ぼしている。
- 工期への影響: 特に移動式クレーンのオペレーターやコンクリート圧送作業員など、現場への移動時間も労働時間に含まれるようになった職種では、現場での実質的な作業時間が従来の8時間から6時間程度へと短縮を余儀なくされている。これはプロジェクト全体の工期長期化に直結する 。
- コストへの影響: 労働時間の減少は、労働者一人当たりの実質賃金の低下につながる可能性がある。これを補うための労務単価の上昇圧力は強く、また、工期の延長は現場管理費や仮設費といった間接コストの増加をもたらす 。
- 経営と現場の認識ギャップ: 働き方改革の推進において、経営層は「工期遵守」を最優先事項と捉える傾向があるのに対し、現場の管理職や一般社員は「改革を推進する人材の不足」を最大の障壁と感じており、両者の間には認識の乖離が存在する。このギャップが、実効性のある対策の展開を阻害する一因となっている 。
これらの状況は、建設業がもはや労働力という最も基本的な生産要素に強い制約を抱えるようになったことを意味する。従来の「長時間労働を前提とした工期設定とコスト管理」というビジネスモデルは限界を迎え、生産性の抜本的な向上が唯一の解決策として浮上している。この変革圧力は、後述する建設DXへの投資を「選択肢」から「必須要件」へと変え、技術力と資本力を持つスーパーゼネコンと、そうでない中小建設会社との間の格差をさらに拡大させる要因となる可能性が高い。
1.2 資材価格の動向と利益率への影響
2021年以降、世界的なサプライチェーンの混乱や需要増を背景に、建設資材価格は急騰し、依然として高水準で推移している 。、一般財団法人建設物価調査会の建設資材物価指数によると、特に熱間圧延鋼材の価格は2022年をピークに横ばいから下落基調にあるものの、コロナ禍以前と比較すると依然として高いレベルにある 。これに加えて、物流業界における「2024年問題」が輸送コストを押し上げ、資材価格にさらなる上昇圧力をもたらしている 。
資材価格の変動は、ゼネコンの「調達力」と「交渉力」を新たな競争力の源泉へと変質させた。価格が安定していた時代には、各社の調達コストに大きな差は生まれにくかった。しかし、価格が激しく変動し、先行きが不透明な現在においては、市況を的確に予測し、有利な条件で早期に資材を確保する能力や、発注者との契約に物価スライド条項を盛り込むといったリスクヘッジの交渉力が、直接的に工事採算を左右するようになった。鹿島建設の有価証券報告書では、こうした建設コストの変動リスクへの対策として、早期調達、多様な調達先の確保、契約への物価スライド条項の導入などが明記されており、調達業務が単なる購買活動から、高度な市場分析とリスク管理を伴う戦略的機能へと昇華したことを示している 。この能力の差は、今後、各社の利益率の差としてより明確に顕在化していくだろう。
1.3 建設DX(ConTech)市場の拡大と生産性革命
前述の人手不足と働き方改革への対応という強い要請を背景に、建設業界におけるデジタルトランスフォーメーション、すなわち建設DX(ConTech)への投資が急速に拡大している。矢野経済研究所の調査によると、2023年度の国内の建築分野における建設テック市場規模は、前年度比11.7%増の1,845億円に達した。市場は今後も年平均成長率(CAGR)7.4%で成長を続け、2030年度には3,042億円にまで拡大すると予測されている 。
スーパーゼネコン各社は、この潮流をリードすべく、BIMを中核に据えたデジタル化を強力に推進している。鹿島建設はダム工事などで自動化施工技術「A4CSEL®」の実用化を進め 、竹中工務店は大阪・関西万博の現場でBIMとデジタルファブリケーションを駆使し生産性向上を実現している 。これらの取り組みは、単なる業務効率化ツールとしての技術導入にとどまらない。
建設DXは、ゼネコンのビジネスモデルを従来の「建設請負業」から、建物のライフサイクル全体にわたる価値を提供する「ソリューション提供業」へと転換させる大きな可能性を秘めている。BIMや各種センサーから得られる建物に関する膨大なデータは、設計・施工段階だけでなく、竣工後の維持管理・運用段階においても極めて高い価値を持つ。清水建設や竹中工務店のレポートでは、建物のライフサイクル全体での価値提供が戦略として明確に打ち出されている 。これは、建物を「建てて終わり」にするのではなく、竣工後のエネルギーマネジメントや施設管理(FM)といったサービスを提供し、継続的な収益源とする新たなビジネスモデルへのシフトを示唆している。今日の建設DXへの投資は、将来のサービス事業への布石という戦略的な側面を色濃く持っている。
1.4 ESG経営の深化とZEB化への挑戦
脱炭素社会の実現に向けた世界的な潮流の中で、建設業界においてもESG(環境・社会・ガバナンス)経営の重要性が急速に高まっている。その中核的な取り組みが、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の普及である。スーパーゼネコン各社は、自社が設計施工する案件におけるZEB化率について、意欲的な目標を掲げている。例えば、大成建設は2026年度に70% 、大林組は2030年度までに50%以上 、清水建設は2026年度に100%を目標としている 。
しかし、その目標達成への道のりは平坦ではない。現状、日本の非住宅建築物ストック全体に占めるZEBの普及率はわずか2%程度であり、目標との間には大きな隔たりが存在する 。
このZEB化への挑戦は、単なる環境貢献活動という側面だけでなく、ゼネコンの「技術的優位性」と「提案力」を差別化するための新たな主戦場となっている。ZEBの実現には、高度な断熱性能、高効率な省エネ設備、そして太陽光発電などの創エネ技術を最適に統合する、高度なエンジニアリング能力が不可欠である。こうした総合的な技術力を提供できるのは、充実した技術研究所を持つスーパーゼネコンの大きな強みである。さらに、発注者に対して、ZEB化に伴う初期コストの増加を、ライフサイクルコストの削減や企業価値向上といったメリットで上回ることを論理的に示し、納得させるコンサルティング能力が受注の成否を分ける。したがって、各社が掲げるZEB化率の目標達成度合いは、その企業の技術力と営業力の総合力を測る重要な指標となり得る。
第2章:スーパーゼネコン5社の財務パフォーマンス比較分析
本章では、スーパーゼネコン5社の財務データを横断的に比較し、収益性、資本効率、事業構造、財務健全性、そして市場からの評価における各社の相対的なポジションを明らかにする。
2025年決算 スーパーゼネコン財務分析 (2025年3月31日)
| 鹿島建設1812 | 大林組1802 | 大成建設1801 | 清水建設1803 | 竹中工務店※2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時価総額(2025年3月31日) | (百万円) | 1,611,300 | 1,431,400 | 1,208,800 | 959,647 | N/A |
| PER | (倍) | 11.30 | 9.73 | 9.68 | 13.97 | N/A |
| PBR | (倍) | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.05 | N/A |
| 売上高 | (百万円) | 2,911,816 | 2,620,101 | 2,154,223 | 1,944,360 | 1,600,129 |
| 前年売上高 | (百万円) | 2,665,175 | 2,325,162 | 1,765,023 | 2,005,518 | 1,612,423 |
| 前年比売上高 | (%) | 9.25% | 12.68% | 22.05% | -3.05% | -0.76% |
| 営業利益 | (百万円) | 151882 | 143442 | 120160 | 71030 | 53118 |
| 前年営業利益 | (百万円) | 136226 | 79381 | 26480 | -24685 | 45676 |
| 前年比営業利益 | (%) | 11% | 81% | 354% | 黒転 | 16.3% |
| 売上高営業利益率 | (%) | 5.22% | 5.47% | 5.58% | 3.65% | 3.32% |
| 従業員数 | (人) | 21,029 | 17305 | 16,382 | 21,286 | 13,598 |
| 一人あたり売上高 | (百万円) | 138 | 151 | 131 | 91 | 118 |
| 当期純利益※1 | (百万円) | 125,817 | 146052 | 123,824 | 66,015 | 56,154 |
| 有形固定資産 | (百万円) | 588,601 | 737577 | 246,745 | 628,702 | 411520 |
| 純資産 | (百万円) | 1,277,988 | 1210201 | 900,699 | 923,809 | 1,091,382 |
| 総資産 | (百万円) | 3,454,592 | 3042778 | 2,428,837 | 2,523,771 | 2,090,447 |
| ROA | (%) | 3.64% | 4.80% | 5.10% | 2.62% | 2.69% |
| ROE | (%) | 9.84% | 12.07% | 13.75% | 7.15% | 5.15% |
| 有形固定資産回転率 | (回) | 4.95 | 3.55 | 8.73 | 3.09 | 3.89 |
| 営業キャッシュフロー | (百万円) | 30,632 | 85625 | -13,841 | 159,094 | 16,826 |
| 投資キャッシュフロー | (百万円) | -104,836 | 9596 | 10,531 | 7,813 | -43,067 |
| 財務キャッシュフロー | (百万円) | 61,687 | -50593 | -133,769 | -71,102 | -15,148 |
| 自己資本比率 | (%) | 36.4% | 38.1% | 35.7% | 34.1% | 51.9% |
| 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 |
※2:他社は2025年3月期となるが、竹中工務店は2024年12月期の決算である。非上場のため時価総額、PER、PBRは算出していません。
2.1 収益性と成長性の比較
2024年度の業績を見ると、鹿島建設が売上高2.9兆円で業界トップの座を維持した 。利益面では、大林組と大成建設がそれぞれ1,400億円台、1,200億円台の当期純利益を確保し、高い収益力を示した 。特に大成建設は、前期に計上した建築事業での大規模損失からV字回復を遂げた点が注目される 。一方で、清水建設は売上高1.9兆円に対し当期純利益が660億円と、他社比較で利益水準が低く、収益性の改善が引き続き課題となっている 。
ただし、当期純利益の額面を比較する際には注意が必要である。2024年度の業績は、「本業である建設事業の採算改善」と、「資産売却やM&Aに伴う一時的な利益」という二つの要素が複雑に絡み合っている。例えば、大林組の当期純利益が1,460億円と5社中トップとなっている背景には、計画を上回るペースで進んだ政策保有株式の売却に伴う特別利益が大きく寄与している 。同様に、大成建設の増益要因にはM&Aに伴う負ののれん発生益が含まれている 。したがって、各社の持続的な収益力を評価するためには、一時的要因が排除される営業利益段階での比較や、後述する事業セグメント別の利益率を精査することが不可欠である。
2.2 資本効率性と市場評価
近年の株式市場からの要請を背景に、スーパーゼネコンの経営目標は、従来の「売上規模の拡大」から「資本効率(ROE)の向上」へと明確にシフトしている。この変化は、各社の財務戦略や市場評価に顕著に表れている。
ROEでは、大成建設(13.8%)、大林組(12.6%)が特に高い水準を達成した 。これは、一般的に株主が期待する資本コスト(7~8%程度)を大きく上回るものであり、資本を効率的に活用して収益を上げていることを示している。この背景には、積極的な自己株式取得や資産売却による自己資本のコントロールが奏功していることがある 。鹿島建設もROEを役員報酬の評価指標に採用するなど、全社的に資本効率を重視する姿勢を鮮明にしている 。
市場からの評価を示すPBR(株価純資産倍率)は、上場4社すべてで1倍を超えており、市場が各社の純資産価値以上の成長性を評価していることを示唆している 。
一方で、非上場の竹中工務店は自己資本比率が51.9%と極めて高く、財務の安定性を最優先する経営方針がうかがえる 。これは、短期的な株主からのプレッシャーを受けない非上場企業ならではの戦略であり、厚い自己資本を背景に長期的な視点での経営を可能にしている。
2.3 事業セグメント別分析
各社の収益構造を理解するためには、事業セグメント別の業績を比較することが不可欠である。スーパーゼネコンの事業は、大きく「建設事業(土木・建築)」と「開発事業(不動産等)」に大別される。
事業セグメント別売上高及び営業利益(率)
| 会社名 | 事業セグメント | 売上高(億円) | 営業利益(億円) | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 鹿島建設 | 土木事業 | 4,041 | 357 | 8.8 |
| 建築事業 | 10,529 | 512 | 4.9 | |
| 開発事業等 | 979 | 278 | 28.4 | |
| 国内関係会社 | 2424 | 164 | 6.7 | |
| 海外関係会社 | 11,143 | 201 | 1.8 | |
| 大林組 | 建設事業 | 24,969 | 1251 | 5.0 |
| 不動産事業 | 729 | 161 | 22.0 | |
| その他 | 503 | 22 | 4.3 | |
| 大成建設 | 土木事業 | 6,306 | 831 | 13..2 |
| 建築事業 | 13,726 | 113 | 0.8 | |
| 開発事業 | 1,376 | 235 | 17.0 | |
| その他 | 134 | 23 | 17.2 | |
| 清水建設 | 建設事業 | 13667 | 193 | 14.1 |
| 開発事業等 | 531 | 169 | 31.8 | |
| 道路舗装事業 | 1508 | 99 | 6.5 | |
| その他 | 3737 | 249 | 6.6 | |
| 竹中工務店 | 建設事業 | 14,496 | 398 | 2.7 |
| 開発事業 | 766 | 90 | 11.7 | |
| その他 | 739 | 40 | 5.4 |
- 土木事業: 利益率の高さが際立つのは大成建設(13.9%)と大林組(10.1%)である。鹿島建設も単体ベースでは15.4%と非常に高い利益率を誇っており、各社の収益基盤となっている 。
- 建築事業: 5社に共通する課題として利益率の低さが挙げられる。特に大成建設は、前期の大規模損失からは回復したものの、依然として0.8%と低い水準にとどまっている。資材価格や労務費の高騰が利益を圧迫する構造的な課題を浮き彫りにしている。
- 開発事業: 建設事業に比べて格段に高い利益率を誇り、各社の業績を下支えしている。特に鹿島建設は、海外(米国)の流通倉庫開発事業が大きな成功を収め、強力な収益源となっている 。大成建設、竹中工務店も開発事業の売上構成比が高く、重要な事業ポートフォリオの一部を形成している。
このセグメント分析から見えてくるのは、「不動産開発事業」の巧拙が、変動の激しい建設事業の利益率を吸収し、企業全体の収益安定性を左右するバランサーとしての役割を強めているという事実である。建設事業、特に建築事業は外部環境の変化を受けやすく収益が不安定になりがちだが、不動産開発事業は賃貸収入など安定したキャッシュフローを生み出し、利益率も高い。各社の決算説明会資料でも、開発事業の業績への貢献が強調されており 、ポートフォリオにおける開発事業の比率と収益性は、その企業の景気耐性を測る上で極めて重要な指標となっている。
2.4 財務健全性の評価
各社の自己資本比率は35%前後で安定的であり、健全な財務基盤を維持している 。中でも非上場の竹中工務店は51.9%と突出して高く、外部資本への依存度が低い強固な財務体質を誇る 。
有利子負債は、不動産開発投資やM&Aを積極的に行う鹿島建設、大林組、大成建設で増加傾向にある 。しかし、これはかつてのような不採算事業を支えるための負債ではなく、将来の収益源となる成長分野への投資を目的とした「戦略的な負債」である点が重要である。各社のキャッシュ・フロー計算書を見ると、投資活動によるキャッシュ・フローのマイナス(支出)を、財務活動によるキャッシュ・フロー(借入)で賄う構図が見て取れる。これは、財務レバレッジを効かせて成長分野に投資し、ROE向上を目指すという、資本効率を意識した財務戦略の表れであり、負債額の多寡だけでなく、その使途を分析することが肝要である。
2.5 キャッシュ・フロー分析
本業での現金創出力を示す営業活動によるキャッシュ・フローは、各社とも堅調な工事代金の回収によりプラスを確保しているものの、大規模工事の入出金タイミングなど運転資本の変動により、年度ごとのブレが大きい 。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、不動産開発、設備投資、M&Aなど、将来の成長に向けた投資により、全社で大幅なマイナス(支出超過)となっている。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当支払いや自己株式取得によるマイナスと、投資資金を賄うための借入によるプラスが混在している。
これらのキャッシュ・フローの動きは、各社が本業で稼いだ現金を内部に留保するのではなく、成長投資と株主還元に積極的に振り向けるという、典型的な成長企業のパターンを示している。これは、各社が中期経営計画で掲げる「成長投資の実行」と「株主還元の強化」という方針が、実際の資金の流れとして着実に実行されていることを裏付けている。
2.6 株主還元策の比較
資本効率向上への強い意識は、各社の株主還元策にも色濃く反映されている。鹿島建設は6期連続の増配を計画し、配当性向40%を目安としている 。大林組はDOE(株主資本配当率)5%程度を目安とし、安定的な配当を継続している 。
特に注目すべきは、大成建設が2025年度より導入する「1株当たり150円を下限とする配当性向30%」という新たな配当方針である 。これは、業績が変動しても最低限の配当を保証するという、株主への強いコミットメントを示すものである。
また、配当に加え、自己株式取得も機動的に実施されている。大成建設は1,500億円、鹿島建設は200億円規模の自己株式取得枠を設定しており 、1株当たりの価値向上を通じて株主価値を高める姿勢を明確にしている。これらの動きは、スーパーゼネコンが単なる建設会社から、株主価値を意識した資本市場のプレーヤーへと変貌を遂げつつあることを示している。
第3章:主要各社の個別詳細分析と戦略評価
3.1 鹿島建設
- 財務ハイライト: 2024年度は売上高2兆9,118億円で業界トップの座を堅持し、4期連続の増収増益を達成した。ROEも10.2%と資本コストを上回る水準を確保し、安定した成長軌道に乗っている 。特に単体の当期純利益は1,047億円と過去最高を更新し、本業の強さを示した 。
- 戦略評価: 鹿島建設の強みは、事業ポートフォリオのバランスの良さにある。国内建築事業の利益率改善(9.6%)を着実に進めると同時に、海外、特に米国の流通倉庫開発事業を大きな収益柱へと育て上げた 。また、ダム工事などで実績を積む自動化施工技術「A4CSEL®」に代表されるように、技術開発への投資を惜しまず、生産性向上という業界全体の課題に正面から取り組んでいる 。中期経営計画では「2030年度の連結当期純利益1,500億円以上」の早期達成を掲げ、6期連続の増配や200億円の自己株式取得計画など株主還元も強化しており、成長、収益性、安定性、株主還元の全てにおいてバランスの取れた戦略を推進している 。
- 受注高・キャッシュフロー・負債: 提出会社単独の受注高は1兆8,311億円 。キャッシュ・フローは、営業CFが306億円のプラスに対し、積極的な不動産開発投資などを反映し投資CFは1,048億円のマイナスとなった。有利子負債は7,920億円となっている 。
3.2 大林組
- 財務ハイライト: 2024年度の売上高は2兆6,201億円。親会社株主に帰属する当期純利益は1,460億円と5社中トップを記録したが、これは計画を上回るペースで進んだ政策保有株式の売却益という特別利益が大きく寄与したためである 。ROEは12.6%と高い水準を達成した。
- 戦略評価: 大林組の戦略は、M&Aを梃子にしたグローバル展開と、再生可能エネルギー事業への注力に特徴がある。米国の建設会社MWH社の連結子会社化により、海外土木事業が大きく伸長し、新たな収益源となっている 。中期経営計画2022では、ROIC(投下資本利益率)とROEを重要指標として掲げ、2024年度はそれぞれ6.4%、12.6%と目標を達成しており、資本効率改善への強い意志がうかがえる 。
- 受注高・キャッシュフロー・負債: 連結受注高は3兆3,572億円と極めて好調であった 。キャッシュ・フローは、営業CFが856億円のプラス、投資CFも資産売却が寄与し95億円のプラスとなった。有利子負債は3,627億円と、積極的な事業展開にもかかわらず抑制されている 。
3.3 大成建設
- 財務ハイライト: 2024年度の売上高は2兆1,542億円。特筆すべきは、前期に計上した国内建築事業での大規模損失から劇的なV字回復を遂げた点である。当期純利益は1,238億円、ROEは13.8%と5社の中で最高の資本効率性を記録した 。
- 戦略評価: 建築事業における受注時採算が大きく回復したことが業績回復の原動力となった 。戦略面では、平和不動産との資本業務提携など、M&Aを活用した事業領域の拡大に積極的である 。株主還元策として、2025年度より「1株当たり150円を下限とする配当性向30%」という新たな方針を導入した点は、株主への強いコミットメントを示すものであり、市場からも高く評価されている 。
- 受注高・キャッシュフロー・負債: 連結受注高は2兆4,375億円 。キャッシュ・フローは、営業CFが138億円のマイナス、投資CFも105億円のマイナスとなった。有利子負債は3,155億円である 。
3.4 清水建設
- 財務ハイライト: 2024年度の売上高は1兆9,443億円。営業利益は716億円、ROEは7.6%と、他4社と比較して見劣りする水準にとどまった 。収益性の抜本的な改善が喫緊の経営課題である。
- 戦略評価: 清水建設の最大の強みは、ZEB化率の目標(2030年度100%)に代表される、環境・サステナビリティ分野における先進的な取り組みである 。この技術的優位性をいかに収益に結びつけていくかが今後の焦点となる。財務戦略としては、政策保有株式の縮減を積極的に進めている 。中期経営計画では2026年度にROE8%以上を目標としており、今後の利益改善策の着実な実行力が問われる局面にある 。
- 受注高・キャッシュフロー・負債: 受注残高に相当する残存履行義務は2兆2,538億円を確保している 。キャッシュ・フローは、営業CFが1,590億円のプラスと好調であった一方、投資CFは78億円のマイナスであった。有利子負債は5,887億円となっている 。
3.5 竹中工務店
- 財務ハイライト: (2024年12月期決算)売上高は1兆6,001億円。非上場企業である竹中工務店の最大の特徴は、51.9%という極めて高い自己資本比率に象徴される圧倒的な財務安定性である 。ROEは5.5%と低いが、これは分厚い自己資本に起因するものであり、短期的な利益追求よりも長期的な視点での経営安定を重視する同社の哲学を反映している。
- 戦略評価: 創業以来の「最良の作品を世に遺し、社会に貢献する」という経営理念に基づき、「設計施工」の強みを最大限に活かし、品質を追求する姿勢を貫いている 。建築という枠を超え、社会全体の持続可能性に貢献する「まちづくり」をビジョンに掲げ、短期的な損益に左右されない長期的な価値創造を目指している 。新たに策定された中期経営計画2030では、「リジェネラティブ(再活性)」をキーワードに、環境共創、技術革新、人材活躍を3つの重点分野として定めている 。
- 受注高・キャッシュフロー・負債: 連結受注高は1兆4,933億円 。キャッシュ・フローは、営業CFが168億円のプラス、投資CFは430億円のマイナスであった。有利子負債は1,091億円と、その規模に対して極めて低く抑えられている 。
第4章:総括と今後の展望
4.1 スーパーゼネコン各社の戦略的ポジショニング
本レポートで分析したスーパーゼネコン5社は、同じ業界に属しながらも、それぞれが異なる強みと戦略的ポジショニングを構築し、激変する事業環境に適応しようと試みている。
- 鹿島建設:総合力・安定成長モデル 建設事業と開発事業、国内事業と海外事業のバランスが取れたポートフォリオを構築し、安定的な成長を実現している。技術開発力にも定評があり、業界のリーダーとして総合力で勝負する。
- 大林組:グローバル・脱炭素モデル 積極的な海外M&Aによりグローバルな事業基盤を拡大し、再生可能エネルギー事業を新たな成長軸として確立しようとしている。資本効率を重視し、事業ポートフォリオの変革を急ぐ。
- 大成建設:資本効率・株主重視モデル 国内の都市再開発で培った強みを活かしつつ、M&Aを効果的に活用。ROE向上を最優先課題とし、下限付き配当など積極的な株主還元策で市場の評価を高める戦略を採る。
- 清水建設:技術・サステナビリティ先行モデル ZEBなど環境・サステナビリティ関連技術で業界をリードし、技術的優位性による差別化を図る。この先行投資をいかに収益化するかが今後の課題である。
- 竹中工務店:品質・長期視点モデル 非上場という安定した経営基盤を活かし、短期的な利益に捉われず、「設計施工」の強みを追求する。品質と「まちづくり」という長期的ビジョンを経営の根幹に据える。
4.2 建設業界の将来を左右する重要課題
今後、スーパーゼネコンを含む建設業界全体の持続的成長を左右する重要課題は、以下の3点に集約される。
- 人手不足の克服: 「2024年問題」によって顕在化した人手不足は、一過性の問題ではなく、日本の人口動態に根差した構造的な課題である。建設DXによる生産性の抜本的な向上が待ったなしの状況であり、技術の導入スピードとその定着度が、企業の競争力を直接的に左右する。
- 収益構造の転換: 伝統的な建設請負事業は、資材価格や労務費の変動に晒されやすく、安定的な高収益を確保することが困難になりつつある。今後は、不動産開発、再生可能エネルギー、コンセッション(公共施設等運営事業)、竣工後の維持管理・運営サービスなど、より安定的で高収益な事業ポートフォリオをいかに構築できるかが、企業の成長性と安定性を決定づける。
- グローバル市場での競争力: 国内の建設市場が長期的には人口減少により縮小が見込まれる中、海外での事業展開は不可欠な成長戦略である。特に、現地企業とのM&Aを通じた事業基盤の確立や、各国の市場特性に合わせた事業モデルの構築が、グローバル市場での成功の鍵となる。
4.3 成功に向けた提言
本分析を踏まえ、建設業界のプレーヤーが今後成功を収めるためには、以下の戦略的視点が不可欠である。
- デジタル人材への戦略的投資: 建設DXを真に推進するためには、BIMツールや施工ロボットといったハードウェアの導入だけでは不十分である。それらを効果的に運用し、得られたデータを分析して新たな価値を創造できるデジタル人材の育成と確保が最優先課題である。外部からの採用と並行し、社内でのリスキリングプログラムを強化すべきである。
- サプライチェーンとの共創関係構築: 資材高騰や人手不足は、自社単独で解決できる問題ではない。協力会社との関係を従来の受発注関係から、リスクと利益を共有するパートナーシップへと転換し、サプライチェーン全体での生産性向上とリスク分散を図る「共創」の視点が求められる。
- 非財務価値の戦略的訴求: ZEBやESGへの取り組みは、もはや単なる社会的責任やコスト要因ではない。これらを顧客への付加価値提案(例:ライフサイクルコストの削減、テナント誘致力の向上)や、企業ブランドの向上、優秀な人材を惹きつける採用力強化に繋げる、戦略的なコミュニケーションが不可欠である。環境性能という非財務価値を、具体的な経済的価値に翻訳して顧客に提示する能力が、今後の受注競争において重要な差別化要因となるだろう。