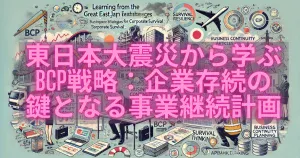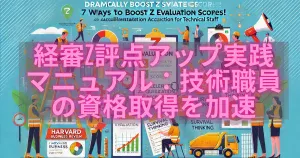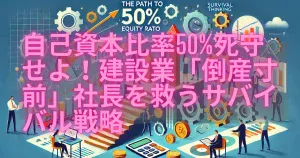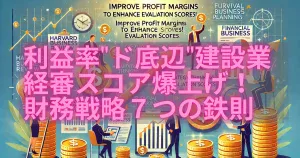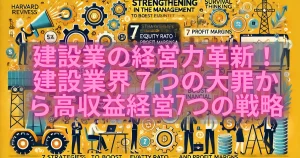第1章 エグゼクティブサマリー及びセクター概観
本レポートは、建設業界向け経営コンサルティング活動の営業戦略策定を目的とし、日本の準大手ゼネコン11社を対象とした2025年3月期(2024年度)の財務諸表に基づく詳細な分析を提供するものである。分析対象は、一般財団法人建設経済研究所の分類に基づく準大手ゼネコン11社、すなわち長谷工コーポレーション、インフロニア・ホールディングス、戸田建設、安藤・間、五洋建設、西松建設、熊谷組、奥村組、高松コンストラクショングループ、東急建設、そして三井住友建設である 。
2025年3月期における準大手ゼネコンセクターは、一見すると堅調な成長を示している。11社合計の連結売上高は前期比7.6%増の5兆9700億円に留まった 。しかし、その一方で連結営業利益は同8.6%増の2,923億円に達し、増収率が利益成長を上回る「マージン圧縮」の傾向がセクター全体で確認された 。これは、資材価格の高騰や人件費の上昇といったコストプレッシャーが、売上拡大の効果を相殺していることを示唆しており、特に売上総利益率は11.6%から11.4%へと微減している 。
さらに深刻な課題として、本分析が明らかにするのは「利益とキャッシュフローの乖離」である。準大手セクター全体の営業利益が増加したにもかかわらず、その事業活動から得られる現金を測る営業キャッシュフローは、前期の2,029億円の黒字から、当期は614億円の黒字へと70%も急減した 。この現象は、建設業界特有の構造的問題を浮き彫りにする。すなわち、会計上の利益は計上されているものの、その代金回収が遅延している(売上債権の増加)、あるいは進行中のプロジェクトに多額の資金が固定化されている(未成工事支出金の増加)といった、ワーキングキャピタル(運転資本)の悪化がセクター全体で進行している可能性が高い。これは、準大手ゼネコンが実質的に顧客やサプライチェーンの非効率性を自社のバランスシートで吸収している状態であり、深刻な流動性リスクと経営機会の損失に繋がる。
本レポートでは、これらのマクロトレンドを個社レベルまで掘り下げ、各社の財務状況、収益性、効率性、そして戦略的意図を解読する。これにより、各社が直面する固有の課題を特定し、それぞれに最適化されたコンサルティング提案の切り口を明確にすることを目的とする。
第2章 準大手ゼコン11社 財務データマトリクス(2025年3月期)
以下の表は、本分析の基礎となる準大手ゼネコン11社の主要財務指標を一覧にしたものである。各社の有価証券報告書、決算短信、および市場データから情報を抽出し、比較分析を可能にするため、主要な経営指標と算出指標を網羅した。これにより、各社の規模、収益性、効率性、財務健全性を横断的に評価するための客観的なデータ基盤を提供する。
注:本表のデータは、各社の公開情報に基づき作成されているが、一部の企業については提供された資料内で全てのデータが確認できなかったため、「N/A」(情報なし)と記載している。時価総額、PER、PBRは2025年3月31日時点の市場データを基にしており、日々変動する。
準大手ゼネコン11社 財務指標一覧(2025年3月期)
| 項目 | 長谷工(1808) | インフロニアHD(5076) | 戸田建設(1860) | 安藤・間(1719) | 五洋建設(1893) | 西松建設(1820) | 熊谷組(1861) | 奥村組(1833) | 高松CG(1762) | 東急建設(1720) | 三井住友建設(1821) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時価総額 (百万円) | 591,060 | 332,012 | 284,583 | 247,274 | 203,355 | 200,599 | 174,440 | 164,133 | 96,343 | 85,088 | 67,834 |
| PER (倍) | 15.56 | 9.21 | 10.51 | 8.09 | 16.12 | 10.8 | 18.49 | 57.38 | 14.93 | 12.71 | 76.51 |
| PBR (倍) | 1.01 | 0.58 | 0.77 | 1.25 | 1.16 | 1.1 | 0.95 | 0.87 | 0.7 | 0.83 | 0.93 |
| 売上高 (百万円) | 1,177,353 | 786,509 | 586,661 | 425,160 | 727,491 | 366,811 | 498,581 | 298,222 | 346,685 | 293139 | 462,982 |
| 前年売上高 (百万円) | 1094421 | 709,641 | 522434 | 394128 | 617,708 | 401633 | 443,193 | 288,146 | 312680 | 285681 | 479,488 |
| 前年比売上高 (%) | 7.6% | 10.8% | 12.3% | 7.9% | 17.8% | -8.7% | 12.5% | 3.5% | 10.9% | 2.6% | -3.4% |
| 営業利益 (百万円) | 84,701 | 51,060 | 26638 | 35243 | 21,697 | 21,098 | 14,299 | 9,731 | 11,460 | 8839 | 7,587 |
| 前年営業利益 (百万円) | 85747 | 44,415 | 17908 | 18591 | 29,152 | 18827 | 12,649 | 13,708 | 11651 | 8155 | 8,500 |
| 前年比営業利益 (%) | -1.2% | 15.0% | 48.7% | 89.6% | -25.6% | 12.1% | 13.0% | -29.0% | -1.6% | 8.4% | -10.7% |
| 売上高営業利益率 (%) | 7.2% | 6.5% | 4.5% | 8.3% | 3.0% | 5.8% | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 3.0% | 1.6% |
| 従業員数 | 8,307 | 7793 | 6,910 | 3,753 | 3888 | 3065 | 4,536 | 2,505 | 4981 | 2845 | 5,392 |
| 一人あたり売上高 (百万円) | 141.73 | 100.93 | 84.90 | 113.29 | 187.11 | 119.68 | 109.92 | 119.05 | 69.60 | 103.04 | 85.86 |
| 当期純利益 (百万円) | 34,450 | 27,411 | 25,185 | 26,444 | 12,460 | 17,581 | 9,354 | 2,722 | 6,453 | 6631 | 855 |
| 有形固定資産 (百万円) | 143,883 | 222507 | 245,795 | 35,440 | 137311 | 182842 | 32472 | 65,164 | 46,816 | 23641 | 36,622 |
| 純資産 | 532,033 | 398521 | 353,197 | 172,183 | 172,121 | 181,190 | 181,829 | 172,455 | 137,756 | 102,667 | 77,315 |
| 総資産 | 1,365,203 | 1363624 | 923,572 | 371,974 | 660,127 | 592,046 | 462,533 | 393,466 | 269,725 | 274,315 | 393,474 |
| ROA (%) | 2.5% | 2.0% | 2.7% | 7.1% | 1.9% | 3.0% | 2.0% | 0.7% | 2.4% | 2.4% | 0.2% |
| ROE (%) | 6.48 | 6.24 | 7.36 | 15.45 | 7.2 | 10.19 | 5.1 | 1.54 | 4.69 | 6.52 | 1.22 |
| 有形固定資産回転率 (回転) | 8.2 | 3.5 | 2.4 | 12.0 | 5.3 | 2.0 | 15.4 | 4.6 | 7.4 | 12.4 | 12.6 |
| 営業キャッシュフロー | 3,916 | 11372 | 26,413 | 11,176 | -23,331 | 5,889 | 8,233 | -11,828 | 5,132 | 41203 | -16,707 |
| 投資キャッシュフロー | -32,472 | -260898 | -61,191 | 1,600 | -23,216 | -36,250 | -11,990 | -1,492 | -1,699 | -1595 | 2,634 |
| 財務キャッシュフロー | -20,545 | 271836 | 7,364 | -5,751 | 43,883 | 16134 | -16,466 | 12,070 | 5,458 | -31878 | -6,916 |
| 自己資本比率 (%) | 39.0 | 28.3 | 37.05 | 46.0 | 26.1 | 29.1 | 39.3 | 45.1 | 51.1 | 37.1 | 17.8 |
| 有価証券報告書URL | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 |
第3章 成長性・規模・収益性の分析
3.1 売上高の動向と市場ポジション
2025年3月期、準大手ゼネコンセクターは平均7.1%の増収を達成したが、その成長の内実は各社で大きく異なる 。五洋建設(17.8%増)、熊谷組(12.5%増)、インフロニア・ホールディングス(10.8%増)はセクター平均を大幅に上回る二桁成長を遂げ、積極的な受注活動や大型案件の進捗が市場シェアの拡大に寄与したことを示している 。一方で、三井住友建設は-3.4%の減収となり、事業ポートフォリオの再編や受注環境の変化に直面している可能性がうかがえる 。また、奥村組(3.5%増)のように、増収ではあるもののセクター平均を下回る伸びに留まる企業も見られる 。この成長率のばらつきは、各社が展開する事業領域(土木、建築、不動産等)の市況や、得意とする工事種別、そして地理的戦略の違いを反映しており、市場内での競争優位性が二極化しつつあることを物語っている。
3.2 収益性とマージン分析
本分析における最も重要な論点の一つが、収益性の格差である。セクター全体の平均売上高営業利益率は4.9%(2,923億円 ÷ 5兆9670億円)と算出されるが、個社のパフォーマンスはこの平均から大きく乖離している 。
この「マージンの二極化」は、各社の経営体質とリスク管理能力を如実に表している。長谷工コーポレーションは、マンション建設に特化したビジネスモデルで7.2%という高い利益率を確保している 。これに続き、インフロニア・ホールディングス(6.5%)、西松建設(5.8%)もセクター平均を上回る健全な収益性を示している 。対照的に、三井住友建設(1.6%)、熊谷組(2.9%)などは、セクター平均を大きく下回る利益率に留まっている 。
利益率の低い企業群は、いくつかの共通した課題を抱えている可能性が高い。
第一に、競争の激しい市場での価格競争による低採算案件の受注。
第二に、予期せぬコスト増(資材高騰、労務費上昇)を適切に価格転嫁できていない契約管理上の問題。
第三に、プロジェクト管理の非効率性による現場レベルでのコスト超過である。
これらの企業は、売上を確保するために利益を犠牲にしている構造的な問題を抱えており、収益性改善を目的としたオペレーション改革や戦略的入札プロセスの構築といったコンサルティング介入の必要性が極めて高い。
資本効率の観点からROE(自己資本利益率)とROA(総資産利益率)を見ると、安藤・間がROE 15.4%、ROA 7.1%と突出したパフォーマンスを示しており、効率的な資本活用と高い収益性を両立している 。一方で、奥村組(ROE 1.54%、ROA 0.7%)や三井住友建設(ROE 1.2%、ROA 0.2%)は、投下資本に対して十分なリターンを生み出せておらず、資本効率の抜本的な改善が経営課題となっている 。
第4章 オペレーション効率と資源活用
企業の競争力は、その最も重要な資源である「人材」と「資産」をいかに効率的に活用できるかにかかっている。この章では、労働生産性と資産効率の観点から各社のオペレーション能力を評価する。
4.1 労働生産性と人的資本
従業員一人当たりの売上高は、事業の効率性を示す重要な指標である。長谷工コーポレーションが一人当たり1億4,170万円と最も高い生産性を示しているのに対し、戸田建設(8,490万円)や三井住友建設(8,560万円)、高松コンストラクショングループ(6960万円)は比較的低い水準にある 。この中間層には、奥村組(1億1,900万円)、安藤・間(1億1,330万円)、熊谷組(1億900万円)などが位置しており、セクター内での生産性には明確な階層が存在する 。
この生産性の格差は、単に事業内容の違い(例えば、労働集約的な土木工事か、付加価値の高い不動産開発か)だけでは説明できない。多くの場合、この差はBIM(Building Information Modeling)やAIを活用した工程管理、ドローンによる測量といった建設テック(ConTech)の導入度合いや、サプライチェーン全体のデジタル化、そして標準化された業務プロセスの成熟度を反映している。
すなわち、一人当たり売上高が低い企業は、デジタル化への対応が遅れ、旧来型の労働集約的なオペレーションに依存している可能性が高い。これは、将来的な人手不足や働き方改革への対応力という点で、重大な経営リスクとなる。したがって、これらの企業に対しては、単なる業務改善提案に留まらず、デジタル技術を核としたビジネスモデル変革や、生産性向上に直結する戦略的テクノロジー投資といった、より付加価値の高いコンサルティングが可能となる。生産性ギャップを競合他社との比較で具体的に示すことは、変革の緊急性を経営層に訴えかける強力な材料となるだろう。
4.2 資産管理と資本集約度
有形固定資産回転率(売上高 ÷ 有形固定資産)は、企業が保有する土地、建物、機械設備といった物理的資産をどれだけ効率的に売上創出に結びつけているかを示す指標である。この数値が高いほど、少ない固定資産で多くの売上を生み出していることを意味する。
熊谷組が15.4回転と極めて高い効率を示しているのは、自社で大規模な設備を保有せず、協力会社とのネットワークを駆使するファブレスに近い経営モデルの特性を反映している 。一方で、戸田建設(2.4回転)や西松建設(2.0回転)は回転率が低く、資本が固定資産に比較的多く投下されていることを示唆する 。
低い回転率は、必ずしも非効率性を意味するわけではない。例えば、自社で大型の建設機械を保有する土木事業中心の企業や、賃貸用不動産を多く保有する企業では、回転率は自然と低くなる。しかし、これが遊休資産や低稼働の設備、あるいは収益性の低い不動産によって引き起こされている場合、それは経営上の大きな問題となる。これらの企業に対しては、保有資産のポートフォリオ最適化、ノンコア資産の売却やセールス・アンド・リースバックによる資金創出、そしてプロジェクトパイプラインの強化による設備稼働率の向上といった、資産効率改善に焦点を当てたコンサルティングが有効である。
第5章 バランスシートの健全性と財務安定性
企業の財務安定性は、経済の不確実性に対する抵抗力や、将来の成長投資に向けた余力を示すものである。自己資本比率は、その中核的な指標となる。
準大手セクターの平均自己資本比率は36.0%であり、これを基準に各社の財務戦略を評価することができる 。高松コンストラクショングループは51.1%という極めて高い自己資本比率を誇り、無借金経営に近い非常に保守的で安定した財務基盤を築いている 。安藤・間(46.0%)や奥村組(45.1%)も同様に、セクター平均を大幅に上回る健全な財務体質を有している 。
一方で、三井住友建設の自己資本比率は17.8%とセクター内で著しく低い水準にある 。これに続き、五洋建設(26.1%)も平均を下回っており、事業運営を借入金などの負債に比較的大きく依存していることを示し、金利上昇や金融市場の変動に対して脆弱な財務構造であることを意味する 。
企業の資本構成は、単なるリスク指標ではなく、その戦略的意図を反映する鏡である。高松コンストラクショングループのような財務的に保守的な企業は、安定性を最優先する一方で、手元の潤沢な資本を成長投資に活かしきれていない「資本の非効率性」という課題を抱えている可能性がある。このような企業への提案は、M&Aや新規事業開発、大規模な技術投資など、その強固な財務基盤を活かした「成長戦略のアクセラレーション」が中心となる。
対照的に、三井住友建設のような財務レバレッジの高い企業にとっては、リスク管理と財務体質の改善が最優先課題となる。提案の焦点は、運転資本の効率化によるキャッシュ創出、不採算事業からの撤退、そして事業ポートフォリオの見直しを通じた財務リストラクチャリングといった「企業価値の防衛と再生」に置かれるべきである。このように、自己資本比率を基点として企業を分類することで、各社の経営課題に即した、説得力のあるコンサルティングアプローチを構築することが可能となる。
第6章 キャッシュフローの動向と戦略的意図の解読
損益計算書が企業の「収益性」を示すとすれば、キャッシュフロー計算書は企業の「生命線」である現金創出力と、その資金使途から透けて見える「戦略的意図」を明らかにする。
6.1 事業の根源的キャッシュ創出力(営業キャッシュフロー)
エグゼクティブサマリーで指摘した「利益とキャッシュフローの乖離」は、個社レベルでさらに顕著となる。最も象徴的な事例が奥村組である。同社は2025年3月期に97億円の営業利益を計上しながら、営業キャッシュフローは118億円のマイナス(赤字)であった 。これは、利益として計上された金額を215億円も上回る現金が、運転資本(売上債権や棚卸資産)の増加として社外に流出、あるいは社内に滞留したことを意味する。このような状況は「黒字倒産」のリスクを内包する危険な兆候であり、運転資本管理とプロジェクトのキャッシュサイクルマネジメントが喫緊の経営課題であることを示している。
同様に、五洋建設も217億円の営業利益に対して営業キャッシュフローが233億円のマイナスとなっており、大規模プロジェクトにおける資金繰りの課題を抱えていることが推察される 。これらの企業は、セクター全体が直面するキャッシュフロー悪化の中でも特に深刻な状況にあり、キャッシュフロー改善を目的としたコンサルティングサービスの最も有力なターゲットとなる。
6.2 投資・財務活動から読み解く戦略
営業キャッシュフロー(OCF)、投資キャッシュフロー(ICF)、財務キャッシュフロー(FCF)の3つの組み合わせを分析することで、企業の現在の戦略的立ち位置を明確に把握することができる。
- 「健全な成長」モデル(OCF:プラス、ICF:マイナス、FCF:マイナス) 長谷工コーポレーションがこの典型である。本業で稼いだ現金(OCF: +39億円)を、将来の成長のための投資(ICF: -325億円)と、株主還元や借入金返済(FCF: -205億円)にバランス良く配分している 。これは、自立的な成長サイクルが確立された成熟企業の理想的な姿である。
- 「借入主導の成長・投資」モデル(OCF:プラス/マイナス、ICF:マイナス、FCF:プラス) このパターンの企業は、本業のキャッシュ創出力だけでは不足する投資資金を、外部からの借入で積極的に賄っている段階にある。成長期にある企業や、大規模な設備投資を行う企業に見られる。
- 「財務改善・事業再編」モデル(OCF:プラス、ICF:プラス、FCF:マイナス) 資産売却など(ICF:プラス)によって得た資金を、借入金の返済(FCF:マイナス)に充てている。事業の選択と集中や、財務体質の改善を優先している段階である。
- 「要警戒」モデル(OCF:マイナス、ICF:マイナス、FCF:プラス) 奥村組がこのパターンに該当する。本業で現金を生み出せていない(OCF: -118億円)にもかかわらず、投資を継続し(ICF: -15億円)、その両方を新たな借入(FCF: +121億円)で賄っている 。これは、事業の根幹が揺らいでいる可能性を示唆する最も危険なキャッシュフロー・プロファイルであり、早急な事業・財務両面での立て直しが不可欠である。
このようにキャッシュフローの構造を分析することで、各社が「成長」「安定」「再建」のどのフェーズにあるかを客観的に診断し、それぞれの状況に合わせた最適なコンサルティング提案を策定することが可能となる。
第7章 総括とコンサルティングエンゲージメントへの戦略的示唆
本分析を通じて、準大手ゼネコン11社は、セクター全体の動向とは別に、各社固有の課題と機会に直面していることが明らかになった。これらの企業を財務特性に基づいて類型化し、それぞれに最適化されたアプローチを策定することが、効果的な営業活動の鍵となる。
7.1 ターゲット企業の類型化
分析結果に基づき、11社を以下の4つの戦略的アーキタイプに分類する。
- 効率的経営者 (Efficient Operators):
- 該当企業例: 長谷工コーポレーション、安藤・間
- 特徴: 高い利益率とROE、安定したキャッシュフロー創出力、高い労働生産性。
- 課題/機会: 既存事業の更なる高度化、M&Aや新規事業による非連続な成長機会の模索。
- 保守的安定企業 (Conservative Incumbents):
- 該当企業例: 高松コンストラクショングループ
- 特徴: 極めて高い自己資本比率、低い財務リスク、安定しているが比較的低いROE。
- 課題/機会: 強固な財務基盤を活かした成長戦略の策定と実行(資本効率の向上)。
- キャッシュフローに課題を抱える成長企業 (Strained Growers):
- 収益性改善が急務な企業 (Turnaround Candidates):
- 該当企業例: 三井住友建設
- 特徴: 低い営業利益率とROE、高い財務レバレッジ。
- 課題/機会: コスト構造改革、不採算事業の見直し、入札戦略の高度化、財務リストラクチャリング。
7.2 類型別エンゲージメント戦略と具体的アプローチ
各類型に対して、以下のデータに基づいた具体的なアプローチが考えられる。
- 対「効率的経営者」:
- 提案内容: DX(デジタルトランスフォーメーション)の更なる推進、サステナビリティ経営の高度化、M&A戦略支援。
- 具体的アプローチ: 「業界トップクラスのROE を達成されていますが、次の成長ドライバーとして、建設テック分野のスタートアップとの連携や、海外の未開拓市場への進出をご支援できないかと考えております。M&Aアドバイザリーチームが、戦略的フィットの高いターゲットをリストアップし、実行までをサポートいたします。」
- 対「保守的安定企業」:
- 提案内容: 資本配分戦略の最適化、新規事業開発支援、株主価値向上策の立案。
- 具体的アプローチ: 「自己資本比率51%という鉄壁の財務基盤は、大きな強みです。一方で、この潤沢な資本を活用しROEをセクター平均以上に引き上げることで、企業価値は飛躍的に向上するポテンシャルがあります。再生可能エネルギー事業やインフラ運営事業など、コアコンピタンスを活かせる新規成長領域への戦略的投資計画の策定をご支援します。」
- 対「キャッシュフローに課題を抱える成長企業」:
- 提案内容: ワーキングキャピタル最適化、プロジェクト・ライフサイクル全体でのキャッシュマネジメント導入、リスク管理体制の強化。
- 具体的アプローチ(奥村組の例): 「2025年3月期のデータでは、97億円の営業利益に対し、営業キャッシュフローがマイナス118億円と、約215億円のギャップが生じています。これは、セクター全体の営業キャッシュフローが半減する中でも特に深刻な状況であり、価値ある現金が運転資本に滞留していることを示唆します。弊社の専門チームは、この『眠っている現金』を解放するキャッシュコンバージョンサイクルの短縮化に実績があり、貴社の財務体質を劇的に改善できると確信しております。」
- 対「収益性改善が急務な企業」:
- 提案内容: 全社的コスト削減プログラム、調達・購買プロセスの改革、戦略的プライシングと入札モデルの構築。
- 具体的アプローチ(三井住友建設の例): 「貴社の営業利益率1.6%は、セクター平均の4.8%と比較して改善の余地が大きいと考えられます。資材調達から現場の工程管理、間接費に至るまで、バリューチェーン全体を精査し、利益率を数ポイント改善するための具体的な実行計画を、我々は過去の多数の建設会社支援実績に基づき策定・実行することが可能です。」
以上の通り、客観的な財務データに基づき各社の状況を深く理解し、それぞれの課題に寄り添った仮説を提示することが、信頼を獲得し、高付加価値なコンサルティング契約へと繋げるための第一歩となる。
第8章 準大手ゼネコン11社 個別企業分析
本章では、前章までの全体分析を踏まえ、準大手ゼネコン11社それぞれについて、その財務的特徴、戦略的立ち位置、そして潜在的な経営課題を個別に掘り下げて分析する。
8.1 長谷工コーポレーション (1808)
準大手ゼネコンの中で売上高(1兆1,773億円)、時価総額(5,910億円)ともにトップを誇る業界のリーダーである 。マンション建設に特化したビジネスモデルは、7.2%という高い営業利益率と、従業員一人当たり1億4,170万円という極めて高い労働生産性を実現している 。有形固定資産回転率の8.2回転という高さは、自社で大規模な設備を持たないファブレスに近い経営がいかに効率的であるかを示している 。キャッシュフローは、本業で得た現金を将来への投資と株主還元にバランス良く配分する「健全な成長」モデルの典型であり、経営の成熟度がうかがえる 。まさに、特定分野における卓越したオペレーションで業界を牽引する存在と言える。
8.2 インフロニア・ホールディングス (5076)
長谷工に次ぐ売上規模(7,865億円)を持ち、前期比10.8%の増収、同15.0%の営業増益と、力強い成長を見せている 。6.4%という営業利益率もセクター平均を上回っており、成長と収益性を両立している点は高く評価できる 。一方で、PBRが0.58倍と1倍を大きく割り込んでいるのは、市場が同社の資産価値を十分に評価しきれていない可能性を示唆している 。キャッシュフローは、巨額の投資を外部からの資金調達で賄う「借入主導の成長」フェーズにあり、再生可能エネルギー事業などへの積極的なM&A戦略を反映している 。
8.3 戸田建設 (1860)
安定した財務基盤(自己資本比率37%)を持つ、資産集約型の企業である。特筆すべきは、612億円という巨額の投資キャッシュフロー(マイナス)であり、これは浮体式洋上風力発電事業といった未来への大規模な先行投資を物語っている 。この投資を、264億円の潤沢な営業キャッシュフローで一部賄っている 。一方で、有形固定資産回転率は2.4回転と極めて低く、一人当たり売上高も8,490万円と低い水準にあり、資産と人材の効率性向上が今後の課題となる 。
8.4 安藤・間 (1719)
収益性と資本効率において、他社を圧倒する「効率的経営者」である。ROE 15.4%、ROA 7.1%はいずれも準大手トップであり、営業利益率も8.3%と極めて高い 。46.0%という高い自己資本比率に支えられた盤石な財務基盤と、112億円の安定した営業キャッシュフローを誇る 。まさに優等生と言うべき経営内容であり、今後はこの強固な基盤を活かしてどのような成長戦略を描くかが注目される。
8.5 五洋建設 (1893)
前期比17.8%増という準大手トップの売上成長を達成したが、その代償は大きい 。営業利益は逆に25.6%も減少し、利益率は3.0%まで低下した 。さらに深刻なのは、217億円の営業利益を計上しながら、営業キャッシュフローが233億円ものマイナスに陥っている点である 。これは売上拡大に伴い運転資本が急激に悪化していることを示し、典型的な「キャッシュフローに課題を抱える成長企業」である。自己資本比率も26.1%と低く、財務活動によるキャッシュフロー(借入)で事業運営と投資を賄っており、財務リスクは極めて高い状態にある 。
8.6 西松建設 (1820)
5.8%という高い営業利益率と10.2%という高いROEを両立しており、収益力の高い企業である 。その利益を源泉に、363億円という大規模な投資を積極的に行っており、成長への意欲がうかがえる 。自己資本比率は29.1%とやや低いが、これは成長投資のために意図的にレバレッジを活用している戦略の表れとも解釈できる 。実績ある収益力と積極的な投資を組み合わせた、攻めの経営姿勢が特徴である。
8.7 熊谷組 (1861)
売上高12.5%増、営業利益13.0%増と、インフロニアHDと並びバランスの取れた成長を遂げている 。自己資本比率39.3%という健全な財務基盤を持ち、キャッシュフローも本業の稼ぎで投資と株主還元を賄う理想的な形だ 。同社の課題は、2.9%という営業利益率の低さにある 。この収益性をセクター平均レベルまで引き上げることができれば、企業価値は飛躍的に向上するポテンシャルを秘めている。
8.8 奥村組 (1833)
一見すると自己資本比率45.1%と財務は健全に見えるが、その内情には深刻な課題を抱えている 。営業利益が前期比29.0%減と大幅に悪化していることに加え、97億円の利益を出しながら営業キャッシュフローは118億円のマイナスという危険な兆候が見られる 。これは五洋建設と同様、事業活動で現金が流出していることを意味し、その赤字を借入で補填している状況だ 。表面的な財務指標の良さに隠れた、オペレーション上の重大な問題を解決することが急務である。
8.9 高松コンストラクショングループ (1762)
51.1%という11社中最も高い自己資本比率が示す通り、極めて保守的で安定した財務運営を行う「保守的安定企業」である 。しかし、その安定性と引き換えに、営業利益率は3.3%、ROEは4.7%と収益性・効率性は低い水準に留まっている 。PBRが0.70倍と低いのも、市場がこの「安定しているが成長性に乏しい」点を評価しているためと考えられる 。潤沢な自己資本をいかにして成長投資に振り向け、資本効率を高めていくかが最大の経営課題である。
8.10 東急建設 (1720)
準大手の中では比較的小規模ながら、特筆すべきキャッシュ創出力を持つ「キャッシュカウ」である。営業利益率は3.0%と低いものの、412億円という巨額の営業キャッシュフローを生み出している。これは、売上債権の回収や未成工事支出金の管理といった、運転資本管理が極めて優れていることを示唆する。自己資本比率も37.1%と高く、財務は安定している 。派手な成長よりも、堅実なキャッシュ創出と株主還元を重視する経営方針がうかがえる。
8.5 三井住友建設 (1821)
財務的に最も厳しい状況に置かれている「収益性改善が急務な企業」である。売上・利益ともに前年割れし、営業利益率はわずか1.6% 。ROEも1.2%と、資本が有効に活用されているとは言い難い 。自己資本比率は17.8%と11社中最も低く、財務的な脆弱性が際立つ 。しかし、そのような状況下でも167億円の営業キャッシュフローを確保している点は、事業の根幹にはまだキャッシュ創出力が残されていることを示す一筋の光明である 。
無料コンサルティングのお知らせ

現在、期間限定で初回60分の無料財務診断も実施中です。
以下のような課題をお持ちの経営者様は、ぜひお気軽にお申し込みください。
✅ 自社の財務水準が業界内でどのポジションか知りたい
✅ ROEや利益率を向上させる具体的な方法を知りたい
✅ 準大手ゼネコンレベルの財務体質を目指したい
✅ 銀行融資や経審での評価を高めたい